「またやっちゃた」ということはよくあるような気がします。しかし、具体的にと言われたらすぐに出てきませんでした。テレビを見ていて、夏休み、宿題というやり取りを見ていて思い出しました。沿い言えば、「夏休みの宿題がぎりぎりになるまでやれない」ということを毎年のように繰り返していました。すぐには思い出せないけど、「またやっちゃった…」ということは少なくはないと思います。
例えば、「ダメな相手だとわかっているのに、同じタイプのパートナーを選んでしまう。」という話はよく聞きます。また、「外れると薄々感じているのに万馬券を狙ってしまう」なども聞いたことがあります。そこで、今回のブログは、「なぜ『わかっているのに』同じ失敗を繰り返してしまうのだろうか?」というテーマにしました。以下に、このような行動をしてしまう心理について調べた内容を説明させていただきます。
同じ過ちを繰り返す心理
サンクコスト効果(埋没費用効果):「もったいない」が失敗を増幅させる
すでに費やした時間、お金、労力(サンクコスト=埋没費用)が「もったいない」と感じます。そして、それが無駄にならないようにと、合理性のない判断を続けてしまう心理がサンクコスト効果です。
- 具体例:
- 映画鑑賞:つまらない映画でも、「せっかくお金を払ったから」と最後まで見てしまう。
- プロジェクト:失敗が明らかなプロジェクトでも、「これまでの努力が無駄になるから」と撤退できない。そして、さらに損失を拡大させてしまう。
- 人間関係:多くの時間と感情を費やした関係を、「今さらやめられない」と続けてしまう。
理由:サンクコストに囚われることで、その後の選択が非合理になります。そして、結果的に「また同じ失敗だ」という なぜ同じ過ちになる状況を生み出してしまいます。
確認バイアス(確証バイアス):「見たい現実」しか見ない思考の罠
自分の信じていることや仮説を裏付ける情報ばかりを集めます。そして、反対意見や都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりする傾向のことが確認バイアスです。
- 具体例:
- 占いや相性診断:良い結果だけを信じ、悪い結果は「たまたまだ」と無視する。
- 新しい健康法:効果があったという体験談だけを信じ、科学的な根拠やリスクを調べようとしない。
理由:過去の失敗の原因を、都合の良い理由(例:「今回は運が悪かっただけ」等)に結びつけます。そして、本当の原因(自分の行動や判断)を見ようとしません。その結果、根本的な改善に至らず、同じパターンを繰り返します。
正常性バイアス:「自分だけは大丈夫」という危険な思い込み
異常事態や危険を目の当たりにしても、「これはいつものことだ」「自分は大丈夫」と思い込みます。そして、現実を過小評価してしまう心理が正常化バイアスです。
- 具体例:
- 災害時:津波警報が出ているのに、「まさかここまでは来ないだろう」と避難が遅れる。
- 健康習慣:体に悪いとわかっていても、「自分はまだ若いから大丈夫」と過信して生活を改めない。
理由:「今回は大丈夫だろう」という根拠のない楽観性を持ちます。それにより、過去の失敗から学ぶ機会を逸してしまいます。リスクを正確に認識できないため、根本的な対策を講じることができません。そして、結果として同じ状況に陥ってしまいます。
過ちを繰り返さないために
- 客観的な視点を持つ:信頼できる第三者(友人、家族、専門家)に意見を聞きます。これにより、サンクコストや確認バイアスから抜け出すヒントを得る。
- データや記録をつける:過去の失敗を記録し、感情を抜きにして客観的に原因を分析する。
- 小さな一歩を踏み出す:「完璧な解決策」ではなく、まずは「いつもと違う選択」を試してみる。
- 「失敗」を「学習」と捉え直す:失敗を恥ずかしいことではなく、成長のための貴重なデータだと捉え直す。
まとめ
「またやっちゃた…」を繰り返してしまう要因となる心理を3つ示しました。それは、サンクコスト効果、確認バイアス、正常化バイアスでした。また、それぞれの要因に対して人によって当てはまる程度は異なるものと考えられます。私の場合は、サンクコスト効果、確認バイアスについては思い当たることがほとんどありません。しかし、正常化バイアスは思い当たることが多くあります。このように、人によって当てはまる心理が異なります。そのため、「またやっちゃた…」対策については、自分自身の要因を考えながら、自分にあった対策を立てて試行錯誤をする必要があると思われます。
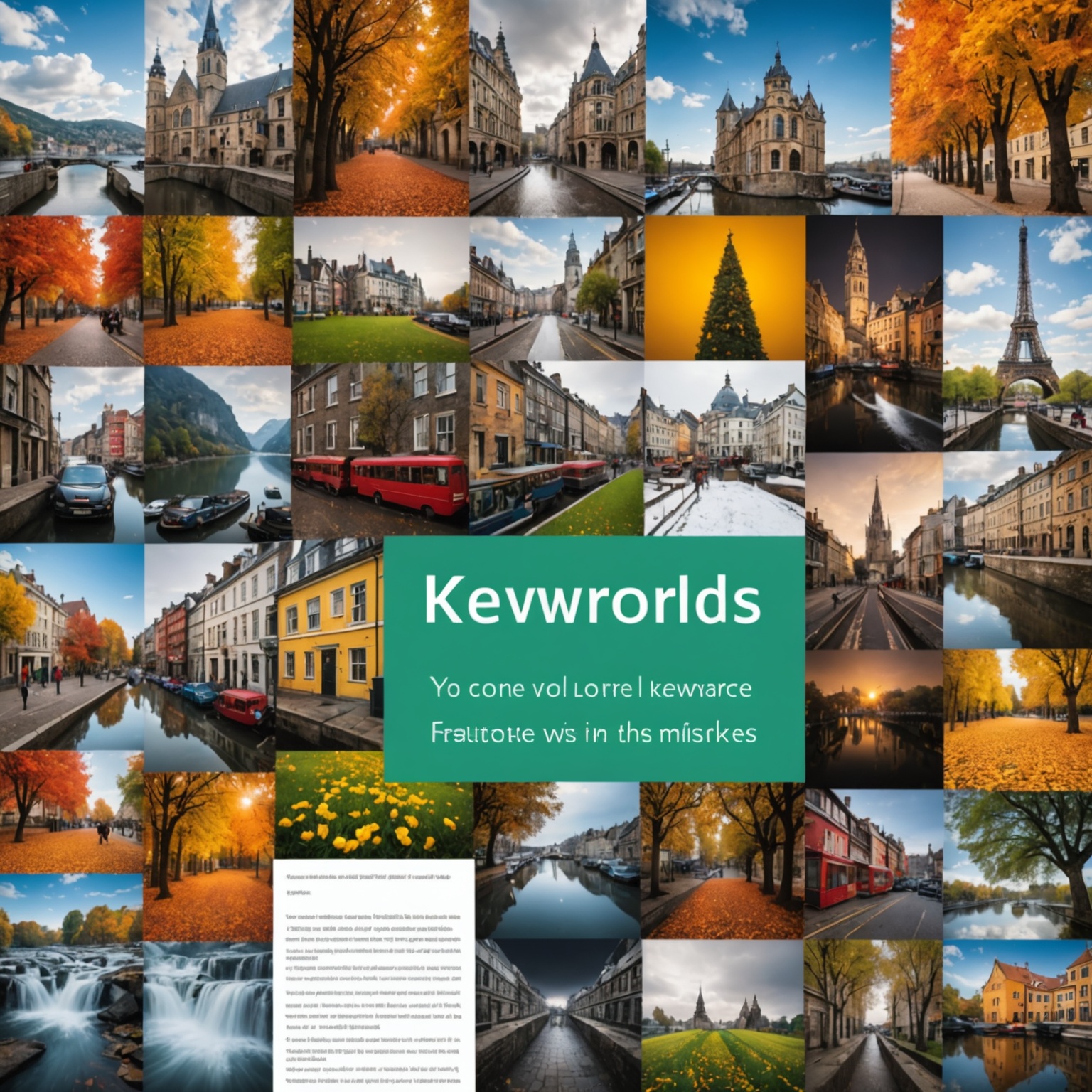


コメント