以前のブログでわかりましたにも色々なレベルがあることを説明しました。「「わかりました!」をどうとらえるか」そして、どのレベルでも「わかっている」、「理解している」と感じていることを示しました。そして、なぜ同じ情報を見ても、『わかる』レベルが違うというところまでは示しました。今回は、「『わかった!』と感じる瞬間、脳の中では何が起きているのか」に注目します。続いて、以下に何が「わかる」と「わからない」を分けているのかについて説明します。
「わかる」と「わからない」を分ける脳の働き
パターン認識:バラバラな情報を「まとまり」として理解する
脳は、五感から入ってくる膨大な情報を、過去の経験や記憶と照らし合わます。そして、これを「パターン」として認識する働きがあります。初心者は注目している個々の情報しか見えません。しかし、熟練者はその背後にある全体像のパターンを瞬時に読み取りることができます。
- 具体例:
- 将棋の初心者は、一つひとつの駒の動きをバラバラにしか見ていません。
- プロ棋士は、盤面全体を「有利な形勢」「危険なパターン」といったまとまりを捉えます。そして、これを一瞬で認識します。つまり、このパターンのデータベースが、脳内に膨大に蓄積されているので可能になっています。
理由:脳がパターンを認識すると、個々の情報を一つひとつ処理する必要がなくなります。これにより、より効率的に、より深いレベルで情報を理解できるようになります。
スキーマ(認知の枠組み):情報の整理棚を作る
スキーマとは、私たちが持つ知識や経験を整理するための「認知の枠組み」です。そして、新しい情報が入ってくると、脳内の既存のスキーマに当てはめて理解しようとします。
- 具体例:
- 野球のルールを知っている人は、初めて見る野球の試合でも「打者が三振した」「ランナーが盗塁した」といった出来事をスムーズに理解できます。それは、脳内に「野球」というスキーマがあるからです。
- ルールを知らない人は、何が起きているのかが分からず、「わからない」と感じてしまいます。
- 学習:新しいことを学ぶことは、新しいスキーマを作るプロセスです。そして、既存のスキーマを修正したりするプロセスでもあります。
理由:スキーマという「整理棚」があるります。それにより、新しい情報を効率的に処理し、既存の知識と結びつけて深い理解を得ることができます。
ワーキングメモリと長期記憶の連携:情報の高速道路を築く
ワーキングメモリは、一度に処理できる情報量が限られています(例:電話番号を一時的に覚える)。一方、長期記憶は、過去の経験や知識が蓄えられている場所です。
- 初心者は、ワーキングメモリで個々の情報を処理します。そのため、すぐに容量がいっぱいになってしまいます。
- 熟練者は、長期記憶に蓄積された知識とワーキングメモリを高速で連携させます。そして、これにより、少ない情報量で多くのことを処理できるようになります。
- 具体例:
- 車の運転:初心者は、アクセル、ブレーキ、ハンドル操作など、一つひとつをワーキングメモリで意識的に処理をします。そのために、すぐに疲れてしまいます。
- ベテランドライバーは、これらの操作が長期記憶に自動化されています。そのために、運転しながらでも他のことを考えられます。
理由:長期記憶との連携がスムーズになることで、脳の負担が減ります。それにより、より複雑で高度な思考ができるようになります。これが「わかる」ことの深さや速さにつながります。
「わかる」を増やすためのヒント
- 「パターン」を見つける練習をする:新しいことを学ぶ際は、個々の情報だけでなく、その背後にある共通のパターンや法則を探してみる。
- アウトプットを重視する:学んだことを人に教えたり、文章にまとめたりします。これにより、脳内のスキーマがより強固になる。
- 「チャンク化」を意識する:一度に多くのことを覚えようとせず、意味のある小さなまとまり(チャンク)に分解して覚える。
内容の整理
「わかる」と「わからない」を分けている脳の働きについて説明しました。そこには3つの要素がありました。全体像を捉えるパターン認識、情報の枠組みを作るスキーマ、ワーキングメモリと長期記憶との連携の3つでした。そして、いろいろな実例を含めて説明してきました。加えて、わかるを増やすためのヒントを示しました。
「わかる」とき1
よく考えてみると、ブログ「「わかりました!」をどうとらえるか」で例にあげた繰り返し専門書を読むという行為がそのまま「わかる」を増やす行為に該当していることがわかります。まず、パターン認識の専門書を繰り返し読むことで全体像を把握できた。次に、スキーマの繰り返し専門書を読むことでその分野の知識を増やすことができた。そして、ワーキングメモリと長期記憶の連携として、繰り返し読むことで長期記憶に保存されます。そして、次に出てきた時に、長期記憶からワーキングメモリに読み出されるようになります。これにより、ワーキングメモリと長期記憶の連携ができるようになっています。これは、あくまでも1つの例になる方法ですが「わかる」ために効果があったと考えられます。
「わかる」とき2
また、私なりの解釈でギターを演奏することについて説明します。まず、ギターを始めたばかりの頃は、一つひとつのコードを押さえるだけで精一杯です。しかし、プロのギタリストなどの熟達者は、譜面を見ただけで曲全体を把握し、感情を込めて演奏できます。このようにレベルに差があります。
初心者は、ギターコードを覚えます。これがスキーマの習得に該当し、「わかった」1つの状態になります。また、全体の曲を弾けるように進歩した状態では、コードの流れや曲の雰囲気を理解できるようになります。これが全体を捉えるパターン認識に該当し、これも「わかった」1つの状態になります。そして、コードの押さえ方を覚え、楽譜を見ただけで曲が演奏できるようになります。これがワークングメモリーと長期記憶が連携できる状態に該当し、これも「わかった」の1つの状態になります。「わかった」の数の差がレベルの差になると考えられます。
まとめ
このように「わかる」ためのパターン認識、スキーマ、ワーキングメモリと長期記憶の連携の3つの要素がありました。そして、それぞれの要因をクリアした時に、それぞれの状態で「わかった」という状態になります。つまり、この1つ1つの「わかった」がわかった瞬間になります。そして、この「わかった」の積み重ねの程度で「わかった」「わかる」のレベルが異なると考えられます。

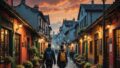

コメント