後になって、これはこういう意味だったのか?その言葉の意味や内容を取り違えていることがあります。これは「思い込み」による影響です。日々の生活の中で、意識的・無意識的に「思い込み」に影響されています。
また、プラシーボ効果も「思い込み」の影響があると思われます。プラシーボ効果とは、患者が「この薬は効く」と信じて薬効成分を含まない偽薬(プラセボ)を服用します。その結果として、偽薬でも実際に症状が改善したり、体調が良くなったりする現象のことです。例えば、子供が怪我をした時に「痛いの痛いの飛んでいけー」で痛みが和らぐことも似たような現象だと思われます。そこでこの「思い込み」について調べてみました。
「思い込み」をしてしまう要因
脳の効率的な情報処理
脳には、五感を通じて常に膨大な量の情報が入ってきています。この情報すべてを毎回ゼロから分析・評価していたら、処理が追いつかないことになります。そして、日常生活を送ることができなくなります。そこで脳は、いろいろな面で脳の情報処理の効率化が行われています。脳では、すべての事を初めてゼロから同じ様に処理することはしていません。過去にあった経験や記憶がある事柄やそれらから類推される事柄については、ゼロからとは別の処理をおこなっています。
スキーマとステレオタイプ
- 脳は、過去の経験や知識に基づいて「スキーマ(認知の枠組み)」と呼ばれるテンプレートを作っています。これにより、情報を整理・解釈します。例えば、「レストラン」というスキーマがるとします。そこには、メニューがある、ウェイターがいる、食事をする場所だ、といった一連の情報を瞬時に理解できます。
- このスキーマが人に対して適用されると「ステレオタイプ(固定観念)」となります。特定のグループの人々に対して、特定の性質や行動を当てはめてしまうことです。これは情報の「型」にはめることで、効率的に理解しようとする脳の働きです。
- 一度形成されたスキーマやステレオタイプは、新しい情報に対し、それに合致するように解釈します。また、反対に合致しない情報が無視されたりする傾向があります。
ヒューリスティック
- 脳は、複雑な問題解決のために「ヒューリスティック(経験則や単純なルール)」を用います。これは、必ずしも論理的に正しいわけではありません。しかし、大抵の場合には役立つ「思考の近道」です。
- 例えば、「値段が高いものは品質が良いだろう」といった直感もヒューリスティックの一種です。これは、必ずしも正しいとは限りませんが、判断を迅速にするのに役立ちます。
認知バイアス
これらの効率的な情報処理の仕組みが、しばしば「思い込み」につながる認知バイアス(思考の偏り)を生み出します。
- 確証バイアス: 自分のすでに持っている信念や仮説を裏付ける情報ばかりを集めます。そして、反証する情報を無視したり軽視したりする傾向です。これにより、思い込みはますます強固になります。
- 利用可能性ヒューリスティック: 思い出しやすい情報(最近見聞きした情報、印象に残った情報など)を、より頻繁に起こる、あるいはより重要だと判断してしまう傾向です。例えば、飛行機事故のニュースを頻繁に見たとします。それにより、実際には自動車事故よりもはるかに稀なのに、飛行機に乗るのが怖いと感じるかもしれません。
- アンカリング効果: 最初に提示された情報(アンカー)が、その後の判断に強く影響を与える傾向です。例えば、セールで「元値10万円が5万円!」と提示されたとします。そのような状況で、5万円が安く感じられるのは、最初の10万円がアンカーになっているためです。
- 後知恵バイアス: 何かが起こった後で、「やっぱりそうなると思った」とすることがあります。それは、あたかも最初から結果を知っていたかのように感じてしまう傾向です。これは、過去の出来事を自分の現在の知識に合わせて再解釈するためです。
- 内集団バイアス: 自分が属する集団(内集団)をひいきし、そのメンバーを肯定的に評価します。その一方で、他の集団(外集団)を否定的に評価する傾向です。これにより、集団内の「常識」や「意見」がそのまま自分の思い込みになることがあります。
感情と動機付け
感情は、私たちの思考や判断に強く影響します。
- 感情的推論: 自分の感じている感情に基づいて、それが事実であると信じてしまう傾向です。不安を感じていると、悪いことが起こると信じ込みやすくなります。
- 自己奉仕バイアス: 自分の成功は自分の能力のおかげ、失敗は外部のせい、と考える傾向です。これは自尊心を保つための思い込みです。
社会的・文化的な影響
私たちは社会的な動物であり、周囲の環境や文化から多大な影響を受けます。
- 社会的学習と規範: 親、教師、友人、メディアなどから、幼い頃から多くの情報や価値観を学びます。これらの情報が、無意識のうちに私たちの信念や思い込みを形成します。社会の「常識」や「当然」とされることが、個人の思い込みとなることがあります。
- 同調圧力: 集団の中で孤立したくないという欲求があります。そのため、周囲の意見や行動に合わせようとする傾向です。たとえ心の中では疑問に思っていたとします。しかし、周りの意見が「正しい」と無意識に思い込んでしまうことがあります。
- 文化的な物語と神話: それぞれの文化には、特定の価値観や信念を伝える物語や神話が存在します。これらは、無意識のうちに人々の世界観や行動様式を形成します。そして、特定の思い込みを強化する役割を果たします。
まとめ
「思い込み」の程度 人により違う
複数の人数に対して同じ物事に対する論理的な説明がされていたとします。この説明に、途中でわかったという人がいます。また、最後まできっちり聞いている人もいます。当然、後で確認して正しく理解している人はいます。しかし、「途中でわかったという人」は後で理解できていない事が分かることが多いような気がします。また、最後までしっかり聞いても、正しく理解できている人とできていない人がいます。この後で理解ができていない事がわかる人に「思い込み」の人が含まれていると思われます。そもそもの前提の知識が不足している人には「思い込み」以前の問題で理解できないことがあるためです。つまり、人によって、物事の内容によって「思い込み」の程度は異なると考えられます。
考察
脳の情報処理の効率化のために思い込みが行われているという調査結果でありました。しかし、「思い込み」と過去に得た知識や経験をごちゃまぜにしない方が良いような気がします。「思い込み」はどちらかと言うとネガティブな印象があります。これとは逆に、過去に得た知識や経験は財産のようなポジティブな印象があります。また、「思い込み」に近いものに「先入観」があるかもしれません。「先入観」も過去の知識や経験に基づき形成されると思われます。また、どちらかと言えばネガティブな印象があります。
次に、「思い込み」が多い人と少ない人がいることに注目します。これらの人の違いは、過去に得た知識がどういう条件やどういう環境下の結果であるかを正しく認識しているか否かが一部関係しているように思えます。過去に得た知識や経験を「汎用」として一般化して使用すると過去の条件と異なる場合は悪影響を及ぼします。つまり、「思い込み」により説明を受けた内容を正しく理解できなくなる可能性があります。
思い込むは大なり小なり誰にもあるような気がします。この過去の知識経験がどの状な条件環境のものかの認識のレベルに依存するように思えます。そのあたりが雑な人は「思い込み」が多くなると思われます。そのため、どういう環境下で、どういう条件でやった結果などを正しく認識することが重要であると感じました。


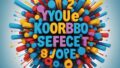
コメント