ステレオタイプについてのブログ「ステレオタイプって?」を書いたことがあります。しかし、一般的な説明を意識して書いたためかステレオタイプの例が少なくなりました。そこで、今回は、ステレオタイプを感覚で理解しやすくために例を多く用いました。加えて、ステレオタイプの弊害という面でアプローチがをしました。以下に、多くの例を用いたステレオタイプ、ステレオタイプの弊害について説明します。
ステレオタイプとは?
特定の集団や個人に対して、単純化され、過度に一般化された固定的なイメージや認識のことを指します。そして、メディアや周囲の環境から形成されることが多く、無意識のうちに私たちの中に刷り込まれてしまうことがあります。また、脳の情報処理を効率化するメリットがある一方で、誤った認識や差別につながるリスクも大きいため、注意が必要です。
具体的な例
次に、いくつかの例を示しますので、ステレオタイプを感覚として理解してみてください。
- 「男性は弱音を吐くべきではない」 「男の子は活発」、「この仕事は男の仕事だから」
- 「女性は家庭的であるべきだ」、「女性は数学が苦手」、「女性は理系に向いていない」
- 「高齢者はITに弱い」、「若者はアナログが嫌い」
- 「あなたには無理そう」、「こうあるべき」、「普通はこう」
- 「外国人は〜」、「特定の国籍の人は犯罪率が高い」、「アジア人は静かでおとなしい」
- 「◯◯人はだらしない」、「△△の人は信用できない」、「◯◯人はルールを守らない」
これらはすべて、個人を見ずに“カテゴリー”で判断してしまう危険な見方です。ただし、「どうせ自分なんかには無理だ」、「私は高卒だから」のような自分に向けたものもあります。
ステレオタイプの弊害とは?
弊害をもたらすステレオタイプについて説明します。その弊害には、無意識の思い込みがもたらす社会への影響があります。また、自分自身に対するものなどもあります。
無意識の思い込みがもたらす社会への影響
個人の可能性を奪う
「あなたには無理そう」「この仕事は男の仕事だから」、「高齢者はITに弱い」:このような言葉が、挑戦する機会を奪い、自信を失わせてしまうことがあります。つまり、本人の意志や能力とは無関係に、外側のイメージによって人生が制限されてしまうのです。
差別や偏見の温床になる
「◯◯人はルールを守らない」「△△出身者は信用できない」「特定の国籍の人は犯罪率が高い」、「◯◯人はだらしない」:このような決めつけは、やがていじめや差別、社会的排除につながる危険性があります。そして、一度広まった偏見は、誤解や敵意を助長し、分断を生み出します。
自分自身への悪影響(自己ステレオタイプ)
他人からの固定観念を受け続けると、自分でもそれを信じ込んでしまうことがあります。そして、これを自己ステレオタイプと呼びます。たとえば、「女の子は数学が苦手」と言われ続けた子どもは、「自分は数学に向いていない」と思い込んでしまうこともあります。また、「男性は弱音を吐くべきではない」と言われ続けた子どもは、「なんでも自分一人で解決しなければならない」と思い込んでしまうこともあります。
多様性と創造性の妨げに
ステレオタイプに縛られると、多様な考え方や価値観を受け入れにくくなります。組織や社会の中で「こうあるべき」「普通はこう」という意識が強いことがあります。これにより、新しいアイデアや柔軟な対応がしづらくなります。例えば、「我が社のこれまでの製品から・・・」という考え方に縛られます。そこで、縛られた範囲外の製品のアイデアが生まれにくくなります。また、「普通はこう」という意識についても言えます。ベテラン社員の「普通はこう」という感覚が、若手社員からの意見を受け入れにくくしています。
無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を強化する
私たちは「自分には偏見はない」と思っていてます。しかし、無意識のうちに誰かを決めつけていることがあります。たとえば、採用面接で「この人は育児中だから負担が大きいかも」と感じてしまいます。そして、「△△の人はルールを守らない」という考えてしまいます。このようなことが、無意識に評価を下げてしまうこともないとは言い切れません。そして、これはアンコンシャス・バイアス(無意識バイアス)と呼ばれます。そして、これはステレオタイプによって強化されることが多いとされています。
別の視点から
家庭などで
TVのバラエティ番組などでの出演者の年齢が表示されることがあります。おそらく、視聴者からの意見で表示されるようになったと思われます。つまり、このような視聴者は「この人は〇〇歳だから・・・」ということに縛られその人個人のことを詳細に見なくなります。また、このような要求をする視聴者は普段の生活でも「この人は〇〇歳だから・・・」という見方をすると考えられます。つまり、常に脳の情報処理の省力化がされています。
また、異なる例では、「東京大学の人、東京大学出身の人は・・・」ということもあります。はじめは、勉強ができるや頭が良いという考えから、「東大出身の人は」、なんでも分かる 、 何でもできるなどのように相手を見なくなっていくことがあります。 このような考え方も、脳の情報処理の省力化がされています。
会社の仕事などで
仕事で設計やプログラムを作成する場合の例について説明します。このような場合には、以前経験した設計やプログラミングコードが影響します。つまり、新しい仕事で、これは前の仕事の「この部分が使える」と考えます。ステレオタイプの傾向が強いほどその内容が一般化されます。それにより、細かい条件を見逃すことが多くなります。そのため、新しい仕事に前の経験を反映した時に必要とする条件を反映することができず不具合になることがあります。このような状態も、脳の情報処理の省力化がおこなわれていると考えられます。
別の例を示します。例えば、10年前の成功体験をそのまま現在の似たような課題に当てはめるということです。それは、取り巻く環境条件は異なっているにも関わらず同じ方法をそのまま適用してしまう行動です。確かに、周りの環境条件の変化が少ない場合は上手くいったように見える場合もあります。しかし、環境条件の変化が大きかった場合は当然うまくいきません。そして、環境要因の変化に気づけずに過去の成功体験の方法をそのまま適用してしまうことも、行き過ぎた脳の情報処理の省力化と捉えることができます。これは、老害と捉えられることもあります。
行き過ぎた脳の情報処理の省力化
脳の情報処理の省力化というものは、脳の働き過ぎを抑制するためのものです。しかし、抑制が行き過ぎると弊害が起こる可能性があります。つまり、脳が働かなすぎの状態を作り出してしまう可能性があります。つまり、これは、脳を使わなくなっていると言えます。
脳を使わなくない行動は、脳の血流量が減った状態を作って、維持していることになります。ここからは科学的根拠はまったくありません。私の仮説?になります。まず、アルツハイマー型認知症は、βアミロイドが脳内に蓄積して発症すると言われています。そして、そのβアミロイドは、通常、血液で脳外に排出されます。アミロイドβを脳の外に出す血流量が、何十年も減った状態が続くとアミロイドβも脳内に蓄積される可能性が高くなると考えられます。そして、これらのことから、ステレオタイプであり続けることが、アルツハイマー型認知症の発症の要因の1つになる可能性があると考えられます。つまり、ステレオタイプの傾向を弱める、排除することで脳内の血流量を減らさないことがアルツハイマー型認知症の予防の一部になると考えられます。
行動の違い
ステレオタイプの脳の情報処理の省力化がおこなわれた場合、目の前の相手の性格を決めつけるため、それ以上に詳しい部分に目(注意)がいかなくなります。しかし、これに対し目の前の相手の様子を見て感じ取る人は、相手の好み、行動、趣味、その人も持つ雰囲気など五感で感じ取ります。このような人が、例えば、プレゼントを送る時、ステレオタイプの人は、一般的にプレゼントとして良いものを選ぶことになります。これに対し、ステレオタイプが弱い人は、相手のことを見ているので、相手が好みそうなプレゼントを選ぶことができます。
これは仕事などの場面でも言えることです。ここれは、例えとして、商品を紹介することにします。まず、ステレオタイプの人は、一般的に妥当な製品についてのプレゼンテーションをします。これに対して、相手のことを見ているステレオタイプの弱い人は、感じ取ってきた相手の要望を満たすようなプレゼンテーションをします。このような違いも生じると考えられます。
対策
まず、自分のステレオタイプの行動に「気づくこと」から変化は始まることになります。例えば、次のような行動です。
- 「本当にその人のことを知っているか?」と自問する
- 多様な立場の人の声を聴く
- 自分の中の思い込みに注意を向ける
- メディアや言葉の使い方に敏感になる
こうした小さな意識の積み重ねが、偏見のない社会へとつながっていきます。また、対策の方法となる内容について以前のブログ 「メタ認知って?」で示しています。ここでは、思い込みを排除するためのメタ認知能力を向上する方法について説明しています。参考にしていただければ幸いです。
まとめ
ステレオタイプの弊害について、個人の制限として挑戦の機会を奪う・可能性を狭めること。そして、差別の温床として偏見が差別やいじめにつながること。自己否定として他人の決めつけを内面化すること。多様性の欠如として、画一的な社会になりやすいこと。そして、判断の歪みとして、無意識の偏見で不公平が生まれることを示しました。
しかし、自分のステレオタイプの考えに気づくことは難しいです。それは、ステレオタイプの傾向が強い人ほど言えることです。ただ、自分で気づいて変化することが必要になります。
ステレオタイプは、便利な近道のようでいて、実は私たちの視野を狭めています。一人ひとりを「個人」として見る目を持つこと。それこそが、社会的にもステレオタイプの弊害が減らせるような気がします。
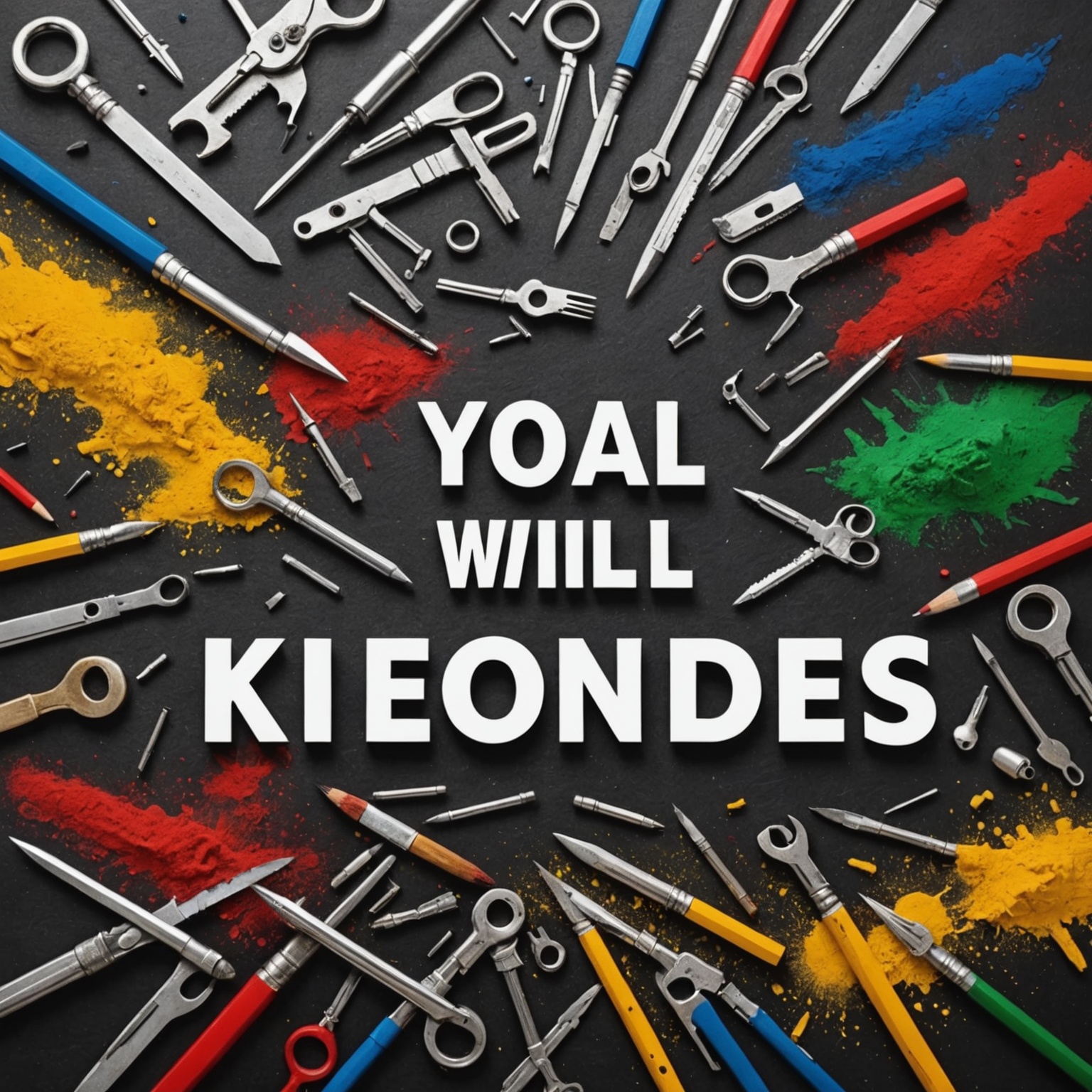

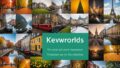
コメント