「思い込み」ブログを書いた時に、ステレオタイプ(stereotype)という言葉がでました。気になっていましたので今回取り上げました。まず、簡単に言うとステレオタイプとは、人間が持っていうる固定観念や偏見のことです。思い込みや先入観などの一部のような気がしています。
そして、もう少し詳しく言うと、ステレオタイプとは、特定の集団や個人に対して、単純化され、過度に一般化された固定的なイメージや認識のことを指します。多くの場合、根拠が乏しかったり、事実とは異なる場合が多いです。しかし、その集団や個人に属する全員がその特徴として思い込む傾向があります。例えば、「女性は感情的だ」「男性は論理的だ」といった見方があります。これは、性別によるステレオタイプがよく知られる例です。
まず、ステレオタイプってどういうものなのか、どういう行動なのかについて調べた結果を示します。そして、まわりにステレオタイプの人がいたらどうするのという視点でも調べてみました。どうにもならない場合もありますが・・・・。
ステレオタイプ概要
特徴
どんなステレオタイプというものがあるか代表的なパターンについて説明します。また、これらのパターンは、それぞれが独立しているというわけではありません。そして、ステレオタイプに対する視点が異なることにより捉え方が変わる一面があることを示しています。
- 単純化と一般化: 複雑な個人や集団の多様性を無視し、数少ない特徴に集約して捉えようとします。
- 固定性: 一度形成されると、なかなか変わらない頑固なイメージです。
- 非現実性: 多くのステレオタイプは、現実とはかけ離れた、あるいは偏った情報に基づいて形成されます。
- 無意識的、自動的: 意識せずに、あるいは自動的に適用されることが多いです。
- 認知的省エネ: 複雑な情報を処理する手間を省くための、ある種の「思考のショートカット」として機能することがあります。
- 感情的要素: 好意や嫌悪といった感情と結びついていることも少なくありません。
例
ここでは具体的なステレオタイプの例を示します。ここに示している例は、全般的には「単純化と一般化」や「無意識的、自動的」が該当しているように思えます。以下のように物事に対して決めつけて捉えるのをステレオタイプということになります。
- 性別に関するステレオタイプ:
- 「女性は感情的である」「男性は論理的である」
- 「女性は家事が得意」「男性は理系科目が得意」
- 国籍・民族に関するステレオタイプ:
- 「〇〇人はみんな働き者だ」「△△人は時間にルーズだ」
- 「××人は数学に強い」
- 職業に関するステレオタイプ:
- 「医者は頭が固い」「教師は真面目だ」
- 「IT企業で働く人はオタクっぽい」
- 年齢に関するステレオタイプ:
- 「若者は常識がない」「高齢者は新しいことに挑戦したがらない」
- 学歴に関するステレオタイプ:
- 「有名大学出身者は優秀だ」「高卒は能力が低い」
もたらす影響
- 偏見と差別の助長: 特定の集団に対する負のステレオタイプは、偏見や差別の温床となります。就職、教育、人間関係など、様々な場面で不利益を生じさせることがあります。
- 自己成就予言 (Self-fulfilling prophecy): ステレオタイプを押し付けられた個人が、その期待に沿うような行動をとってしまう現象。例えば、「自分は数学が苦手だ」というステレオタイプを信じ込まされた学生がいます。その学生について、実際に数学の成績が上がらない、といったケースです。
- 集団内の多様性の無視: 同じ集団に属する人々の個性を無視し、均一な存在として扱ってしまいます。そのため、多様な能力や視点が失われる可能性があります。
- コミュニケーションの阻害: ステレオタイプに基づいた先入観は、相手を正しく理解することを妨げます。そして、これは健全な人間関係の構築を困難にします。
- アイデンティティの抑圧: ステレオタイプに縛られ本来の才能や興味、可能性への抑圧があります。
自分のステレオタイプ対処
- 多様な情報に触れる: 特定の集団に対する情報源を広げ、多角的な視点を持つ。
- 個々人を尊重する: 集団の代表としてではなく、一人の個人として相手を理解しようと努める。
- 自己反省: 自分がどのようなステレオタイプを持っているかを認識する。そして、それが偏見につながっていないか自問自答する。
- 批判的思考: 安易な一般化やレッテル貼りに疑問を持つ。
ステレオタイプの傾向が強い人への対応
ステレオタイプの傾向が強い人との関わり方は、状況によって異なります。その言動の頻度、場所が私的な場か公的な場かなどです。また、その人との関係性をどうしたいかによって変わってきます。ここでは、状況が異なるのでいくつかのアプローチを示します。これらは参考例であり、実際に適用して必ず成功するいうものではありません。あくまでも、例です。相手がどのような状態かによって異なります。そして、その状態は人によって異なるので対応は難しいです。
個人として対話する(穏やかな場合)
相手が比較的穏やかで、対話の余地があると感じる場合、個人的に話してみるのが効果的です。
- 「私」を主語にして伝える: 相手の言動を批判するのではなく、それが自分にどう影響するかを伝えます。これにより、相手も耳を傾けやすくなります。例えば、「〇〇さんが~と言うと、私は少し悲しい気持ちになります」です。この様に「私は」を使用します。また、「その言い方だと、私は~と誤解してしまうかもしれません」も同様な使い方です。
- 具体的に指摘する: 「そういう言い方はやめてください」と漠然と伝えません。『女性だから~』という言い方は、〇〇さんの意図とは異なります。これでは、性別で人を決めつけているように聞こえてしまいますのようにしたほうが良いです。そして、どの部分が問題だと感じるのか具体的に指摘すると良いと思われます。
- 質問を投げかける: 相手に考えさせるきっかけを与えるます。そのために、「それは、なぜそう思われるのですか?」と問いかけます。もしくは、「〇〇さん(ステレオタイプを当てはめている相手)は、本当にそうだと感じていると思いますか?」等のように問いかけてみます。その結果、自分の固定観念に気づくきっかけになるかもしれません。
- 根拠を示す: もし可能であれば、そのステレオタイプが事実ではないことを示す具体的なデータや事例を穏やかに提示するのも有効です。
距離を置く・関与を減らす(難しい場合)
もし相手が頑なで、対話が難しいと感じる、あるいは精神的な負担が大きいと感じる場合は、自身の心を守ることを優先しましょう。社長などの言うことは聞いているが、同僚の言う事には耳を貸さない場合があります。言うことを聞いてくれる人に相談したほうが良いと思われます。自分で説明しても聞いてもらえず、自信が辛くなることがあります。
- 距離を置く: 物理的・精神的に距離を置くことが一番の防御策です。可能な限り、その人との接触を減らしましょう。
- 話題を変える: ステレオタイプな発言が出たら、露骨に批判するのではなく、さりげなく別の話題に切り替えて、その発言に同意しない姿勢を示します。
- 聞き流す・真に受けない: 相手のステレオタイプな発言を真正面から受け止めないこと。そして、「この人はそういう考え方をする人なんだな」と割り切って聞き流すことも必要です。すべての意見に反論する必要はないと考えられます。
- 限定的な関係にする: 仕事上やむを得ず関わる場合は、業務に限定したドライな関係を維持し、プライベートな話は避けるようにしたほうが自分が楽です。
公的な場で対応する(状況に応じて)
- その場で疑問を呈する(丁寧な問いかけ):「それは、〇〇さん(ステレオタイプを当てはめている相手)も同じように感じているとお考えですか?」「その意見の根拠はどこから来ているのでしょうか?」のように、丁寧に疑問を投げかけることで、その発言が一般論として受け入れられるのを防ぐようにする。
- ファクトで反論する: 間違った事実に基づいている場合は、簡潔に正しい情報を提供します。「いえ、私(あるいはデータ)の知る限りでは、それは少し違いますよ」と伝える方法です。
- 上司や人事などへの相談(職場の場合): 職場で継続的にステレオタイプに基づく差別的な発言や行動がある場合は、個人で抱え込まず、上司や人事部門、ハラスメント相談窓口などに相談することを検討してください。これは、あなた自身を守るだけでなく、職場の健全な環境を守るためにも重要と考えられます。
味方を見つける・協力する
- 信頼できる人に相談する: 同じように困っている同僚や友人、家族に相談し、意見を聞いてみる方法です。共感を得られるだけでも気持ちが楽になり、一緒に対応を考えてもらえるかもしれません。
- 集団で対応する: もし複数の人が同じステレオタイプな言動に不快感を持っている場合、個人ではなく集団として働きかけることで、相手に影響を与えやすくなることがあります。
大切なこと
- 安全と心の健康を最優先に: 無理をして対応する必要はないと考えられます。精神的に追い詰められたり、危険を感じるような状況であれば、迷わず距離を置くことが必要と考えられます。
- すべてのステレオタイプを変えることはできない: 一人の力で他人の固定観念をすべて変えるのは非常に難しいと考えられます。もし、その努力が報われなくても、それは対応したの責任ではないと考えられます。
- 自分自身がステレオタイプに加担しない: 周囲のステレオタイプな言動に疑問を持ち、自分自身からステレオタイプな考え方をしないように心がけることが、何よりも重要と考えられます。
まとめ
「ステレオタイプ」という言葉が明確にわかっていないと言うことで調べてみました。その結果、ステレオタイプへの対応を考えた時、非常に重い内容になってしまいました。私も以前ステレオタイプの方への対応で精神的にダメージを受けたことがありました。ステレオタイプの強さによって、対処法で対応できそうな場合もあり、とても対応できないものまでいろいろあるようです。そして、重いステレオタイプに対しての対応として、安全と心の健康の重要視しなければならないことを再認識しました。

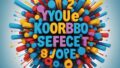

コメント