ことばとして、初頭効果と親近効果は知りませんでした。まず、初頭効果については、初めに良い印象をあたえることです。例えば、面接で相手に良い第一印象を与えます。また、プレゼンテーションやメールで結論を先に伝えます。そして、キャッチコピーや商品パッケージの最初の部分の印象を与えます。これらの初めの印象が記憶に残り、その後の印象を左右することです。他にも、初めてのレストランで素晴らしいサービスが記憶に残り、その後の料理の評価にも影響を与えることなどがあります。
次に、親近効果については、話などの最後が印象に残ることです。例えば、映画の感動的なラストシーンで作品全体の評価を高めます。また、プレゼンテーションで最後に質問への回答を提示して納得感を高めます。そして、旅館の丁寧なお見送りで顧客満足度が上げます。このように、接客で最後にかけた親切な一言が記憶に残ることがあります。
このようなことが初頭効果と親近効果の例です。これらの例は聞いたことがありましたが、名前については知りませんでした。そして、初頭効果と親近効果は、どちらも記憶や印象形成における重要な心理現象で、まとめて「系列位置効果」と呼ばれています。これらは、提示された情報の順序によって、記憶の残りやすさが変わることを示しています。このブログでは、この初頭効果・親近効果がどういうものか、そして、どのようにして使うか、脳内での働き、ピークエンドの法則との違いについて調べましたので、説明をします。
初頭効果・親近効果
初頭効果 (Primacy Effect)
初頭効果とは、最初に提示された情報が、特に記憶に残りやすい心理現象です。私たちは、最初に出会った人や最初に聞いた情報に強い印象を受けます。そして、その後の判断に影響されやすくなります。
- 例: 初めて会う人の自己紹介で、最初に聞いた「誠実」という言葉が強く印象に残ります。そして、その後の話で「少し不器用」な部分があっても、「誠実な人だから、不器用なだけだろう」と良いほうに解釈してしまいます。
- なぜ起こる?: 最初に提示された情報は、他の情報が入ってくる前に短期記憶から長期記憶へと転送されやすいと考えられています。それは、脳は最初の情報を重要だと判断し、より深く処理する傾向があるからです。
親近効果 (Recency Effect)
親近効果とは、最後に提示された情報が、特に記憶に残りやすい心理現象です。最後に聞いたことが、最も新しい情報として鮮明に記憶に残るため、全体の印象を左右することがあります。
- 例: プレゼンテーションの最後に「今なら特別割引を実施中です」という一言を聞きます。そして、それまでの内容よりも最後の情報に強く惹かれてしまいます。
- なぜ起こる?: 最後に提示された情報は、まだ短期記憶に保持されている状態です。そのため、すぐに思い出しやすいと考えられています。特に、情報の提示が終わってすぐに思い出そうとするときに強く作用します。
両者の使い分け
初頭効果と親近効果は、状況によってどちらが強く働くかが異なります。
- 初頭効果が有利な場面: 相手が情報にあまり関心がない場合、記憶する時間がない場合です。最初のインパクトで関心を引きつけたいときに有効です。
- 親近効果が有利な場面: 相手がすでに情報に関心があり、最後に意思決定をする場面です。会議のまとめや交渉のクロージングで、最も伝えたいことを最後に持ってきます。これによりより強く印象づけられます。
この2つの効果を理解し、適切に使い分けるます。これにより、コミュニケーションやプレゼンテーション効果を最大限にすることができます。
脳と初頭効果・親近効果
初頭効果・親近効果は、記憶を司る海馬や、注意・情報処理を担う前頭葉の働きと関係しています。
初頭効果と脳の働き
最初に提示された情報が記憶に残りやすい。それは、脳がその情報を短期記憶から長期記憶に効率よく転送しようとするためです。
- 海馬: 脳の中心部にある海馬は、新しい情報を長期記憶として保存する役割を担っています。最初に提示された情報は、まだ脳が疲れていない状態です。そのため、海馬がその情報をじっくりと処理します。その結果、長期記憶として定着させやすいと考えられます。
- 注意の集中: 情報が提示され始めの段階では、私たちの注意は最も集中しています。この高い集中力が、最初の情報をより詳細に、そして強固に記憶するのを助けます。
親近効果と脳の働き
最後の提示情報が記憶に残りやすいのは、それがまだ短期記憶に保持されているためです。
- 短期記憶の役割: 短期記憶は、一時的に情報を保持する場所で、容量には限りがあります。最後に提示された情報は、この短期記憶にまだ残っています。そのたため、すぐに思い出すことができます。これは、情報の提示が終わった直後に記憶を呼び起こす際に特に強く働きます。
- 脳の疲労: 多くの情報が提示されるにつれて、脳は疲労します。そして、新しい情報を長期記憶に転送する能力が低下します。そのため、直前の情報が短期記憶として残っている状態が、最もアクセスしやすい状態となります。
簡単に言うと、初頭効果は長期記憶への転送、親近効果は短期記憶への保持が主な要因です。そして、その裏で海馬や前頭葉がそれぞれの役割を果たしていると考えられます。
初頭効果・親近効果とピーク・エンドの法則
ピーク・エンドの法則(Peak-End Rule)
ピーク・エンドの法則については、以前のブログ『「ピーク・エンドの法則」― 人の記憶は“最初から最後まで”では決まらない?』で説明しています。ピークエンドの法則は、ある経験全体を評価するとき、私たちはその経験の最も感情が動いた瞬間(ピーク)と最後の瞬間(エンド)の印象だけで、全体の評価を決めてしまうという心理現象です。これは、心理学者ダニエル・カーネマンが提唱したもので、人間の記憶が経験の総量や平均値ではなく、特定の感情的な瞬間に大きく左右されることを示しています。
相違点
ピーク・エンドの法則の対象は、経験全体の評価になります。そして、評価要素は、経験の中で最も感情が動いた瞬間と終わりになります。例としては、映画や旅行全体の満足度を評価することなどです。これに対し、初頭効果・親近効果の対象は、情報の羅列の記憶になります。そして、評価要素は、提示された情報の最初と最後になります。例としては、リストの単語を記憶するなどです。例えば、楽しい旅行の途中で道に迷って最悪な気分になり(ピーク)、最後においしい夕食を食べて終われば(エンド)、旅行全体の評価は「とても良い旅行だった」となります。道に迷った時間が長くても、感情のピークとエンドが良い印象であれば、全体の評価はそれに引きずられます。
このようにピークエンドの対象が、映画や旅行などの全体に対し、初頭効果・親近効果の対象は断片的な情報という大きな違いがあります。
まとめ
ここまで初頭効果・親近効果、どのようにして使うか、脳内での働き、ピークエンドの法則との違いについて説明をしました。そして、脳内の状態として、記憶を司る海馬や、注意・情報処理を担う前頭葉の働きと関係していること。そして、初頭効果は長期記憶への転送、親近効果は短期記憶への保持が主な要因であることを示しました。
また、初頭効果・親近効果の有効的な使い方があります。それは、プレゼンテーションや会議で「最初に聴衆の心をつかみ、最後に最も伝えたいメッセージを強調する」といったテクニックに応用することができます。


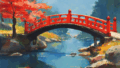
コメント